|
|
|
|
|
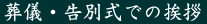 |
|
|
■
|
弔辞のポイント
|
 |
|
|
|
|
弔辞は楷書体できちんと書きましょう
|
 |
|
|
|
弔辞は葬儀の席上、故人に向かって述べることばで、故人や友人や同僚など、故人とゆかりの深い人がのべます。
弔辞は、巻紙や奉書紙に毛筆の楷書体で一字一字きちんと書き、それを読み上げます。読み終えたら霊前に供え、遺族のもとに保管されます。ですから巻紙や奉書紙は左から巻折りにして、表に弔辞と書いた紙に包んで、霊前に捧げます。
|
|
|
故人に呼びかける気持で語ります
|
 |
|
|
|
葬儀は、故人に別れを告げる最後の場面ですから、式場にいる遺族や出席者を意識せずに、あくまでも故人に語りかけるように心のこもった挨拶をすることです。
そのために、「○○さん」「○○君」「○○先生」「○○様、あなたは・・・」というぐあいに、直接故人に呼びかけるような言い方をします。
つまり、故人に別れを告げる儀式が葬儀なのです。
|
|
|
いたずらに涙を誘わないこと
|
 |
|
|
|
意識して遺族や列席者の涙を誘う表現・音声を重ねたり、いたずらに美辞麗句を並べる人がいますが、過度の表現は聞き苦しいものになってしまい、故人の霊も浮かばれません。
たとえ朴訥(ぼくとつ)でも、故人の死を悼み、悲しみの気持ちを素直に吐露したことばの方がいいのです。流ちょうなスピーチよりも、むしろ素朴に心情を吐露したスピーチのほうがふさわしいといえます。
|
|
|
基本形式をふまえること
|
 |
|
|
|
|
しかし、だからといって長々と心情のおもむくままに何もかも語るのでは、マナーに反するといえるでしょう。あくまでも葬儀は一つの儀式なのですから、おのずと儀礼的要素が含まれます。
故人の年齢、職業、家族構成、死亡原因、故人との関係などによって弔辞の内容は異なりますが、厳粛な儀式の基本形式をふまえることを忘れてはなりません。
|
|
|
弔辞の基本形式
|
 |
|
|
|
|
弔辞の長さは様々ですが、一般的には三分程度が適切な長さといえるでしょう。
基本形式を順序だてて説明すると、
(1)哀悼の意を表すことばと、「○○さん」「○○先生」といった故人への呼びかけで始まります。
(2)故人と自分との関係を、簡単に述べます。
(3)故人の生前の業績、人柄、エピソードを、懐かしむように語ります。
(4)自分たちのこれからの誓いと、遺族への慰めや温かい励ましのことばを述べます。
(5)最後に、「ご冥福をお祈りいたします」などの結びのことばで締めくくればよいでしょう。
|
|
|
忌みことばを避ける
|
 |
|
|
|
|
前述したように故人をむやみにほめたり、故人との関係を強調したりするのはマナー違反ですが、それ以外に、繰り返しを意味するような忌みことばも避けなければなりません。
繰り返しを意味することばは、死をくり返すという意味につながるために、忌みことばとなっています。ことば使いには十分注意を払い、ことばを選んでスピーチをすることが肝心といえるでしょう。
忌みことばとは「返す返す」「追って」「重々」「重ね重ね」「なお」「二度」「ふたたび」「いまひとつ」「もう一度」などです。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
■
|
弔辞の例文
|
 |
|
|
|
|
|
|
○美さん、いつも元気いっぱいで、人一倍行動的なあなたが、不治の病に冒されて、闘病生活わずか六ヶ月で逝ってしまったことが悲しくてなりません。
中学で同じクラスになってから、○美さんは私にとって一番付き合いの長い友人でした。中学・高校の頃は、しょっ中けんかもしましたが、それだけ仲の良い証拠だったと思います。
三十年間を振り返ってみて一番の思い出は、新婚まもないころ、ご主人の転勤で引っ越された福岡のお宅へ遊びに行ったときのことです。
あのときはすっかりお世話になりました。車で県内を案内していただいたり、腕をふるった贅沢な食事をごちそうになったり、ご主人と三人で夜の街へ繰り出したり、まだ独身だった私は、○美さんの幸せそうな新婚家庭がうらやましかった。それに、すっかり妻らしさが身に付いたあなたは、光り輝いていました。
○美さんのことを、決して忘れることはないでしょう。どうか安らかにお眠りください。心からご冥福をお祈りします。
|
|
|
|
|
|
|
○○君、君は享年三十五歳の働き盛りでした。しかし、不意の交通事故により不帰の人となられ、私ども一同は驚愕と大きな落胆で、返す言葉もありません。
*「生者必滅、会者定離」は浮き世の定めですが、つい数日前まで元気だった君が、もはや二度と目の前に現れることがないと思うと、現世のはかなさ、悲しさが胸を突きます。
○○君の入社試験の面接の時のことを、今でのはっきりと覚えています。入社の動機、我が社の歴史などを実にさわやかにはきはきと答えられ、仕事に対する情熱を鮮やかに語られたのです。あのときの君の姿は、私の脳裏から一生消えることはないでしょう。
安らかな面影を偲びつつ、ご冥福をお祈りいたします。
*生者必滅、会者定離
生きているものは必ず滅び、会うものは別れるという人生無情のたとえ。
|
|
|
|
|
|
|
謹んで○○ ○○君の御霊前に申し上げます。
○○君と僕は、昭和○○年△△社にともに入社し、知り合って七年四ヶ月でお別れの時が来てしました。○○君は制作部、僕は営業部と畑は違いましたが、妙に気が合い、一生の友と思っていただけに突然の訃報に愕然としています。
クリエイティブな才能の持ち主だった君は、当社若手のコピーライターとして活躍されていました。苛烈な競争の広告業界において、君は少しの気負いもなく、常に毅然と志を守り、マイペースで仕事をされていました。そんな誠実さに好感を持ち、僕たちは公私共々うちとけることができたのです。
一つの大きな仕事が終わると、お互い息抜きによく飲みにも行きました。そして君はいつも口癖のように、「人生は学校だ。そしてそこでの失敗は、成功よりも優れた教師だ」と自分自身に言い聞かせるように、言っていました。僕も、君のこのひと言で、どんなに励まされたことか・・・・・。君の謙虚で前向きな姿勢が、数々の優れたコピーに生きていたのだと思います。
君は真摯な人物であったと同時に、明るくてひょうきんな人柄でした。入社当時から社内の人気者で、とりわけ女性ファンが多かった。奥さんの○子さんとは、二年間の熱烈な社内恋愛の末結ばれたのです。
それだけに残された○子さんの胸中を思うと、せつなさが込み上げます。ここ数ヶ月、君の顔色が悪かったので休養を進めたのですが、君は持ち前に明るさで「残業が続いたからだよ、大丈夫」と受け流しておられました。しかし今思うと、もっと僕が強く注意すれば良かったんだと自責の念にかられます。許してください。
現代医学を持ってしても逃げられない、残酷な運命の触手に、僕は悲しみとともに憤りを感じています。
どうか○○君、残されたご遺族の幸福をあの世からいつまでも見守ってあげてください。僕もできるかぎり尽力をするつもりでいます。
ついに、最後のときが来てしました。ここに△△社同期を代表し惜別の意を捧げます。○○君のご冥福をここをからお祈りいたします。
|
|
|
|
|
|
|
|
本日ここに○○ ○○社長の社葬を行うにあたりまして、社員一同を代表いたしまして、哀悼の意を捧げます。
○○社長の突然の訃報に接し、私たち社員一同はただ驚愕落胆し、悲しみに打ち震えております。私たちにとり、社長はまさに最高のリーダーでありました。威厳に満ちた堂々とした態度、しかもかぎりなく優しかった○○社長の姿が、今も眼前に浮かんでまいります。
○○社長は、一代で当社を築き上げました。三十五歳の時、それまで勤務なさっていた○○商事を退職され、会社を興されたのです。以来三十二年間、戦後の経済試練を乗り越え、さらに高度成長期とともに急成長を遂げ、今や当社はアパレルメーカーのトップクラスにおります。今日の社運の礎を築かれました○○社長は、常に職場の陣頭に立ち、優れた経営手腕を持ったたぐいまれなる事業家といえましょう。
「自信は成功の第一の秘訣である」という言葉がありますが、私たちは○○社長にこの言葉を実感を持って教えていただきました。ビジネスマンたるもの、いかなる事があろうと自分に自信と誇りを持って前進すれば、必ず成功する。たとえ失敗したとしても、プラスに転じる失敗であるというのが、○○社長の信条だったのです。
しかも、寛容で謙虚なお人柄ゆえ、社員の誰にでも「ご苦労さん」のひと言を忘れない。そんな温かい方でした。やはり一流の成功者となるには、自信と誠実さ、この両方を兼ね備えていなければならないことを今改めて感じています。また、○○社長のもとで、働くことができたことを誇りに思っているしだいであります。
今、アパレル業界は厳しく問われている時期にあると言っていいでしょう。過去、幾多の荒波を生き抜いてこられた○○社長の手腕が、今こそ求められているときなのです。それだけに○○社長の急逝は、当社のみならず業界においても、多大な損失であります。まことに無念、断腸の思いであります。
しかし、社長の数々の偉大な足跡は、いかなる事があろうとも不滅だと確信しております。社長の教訓は、私たちの心の中で決して消えることはないでしょう。
私たちにできることは、社長の意志・遺業を受け継ぎ、社員一同一致団結して、ますます社運を発展させることです。○○社長、あの世から私たちを見守り続けてください。
ご冥福をお祈りいたします。
|
|
|
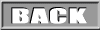 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
